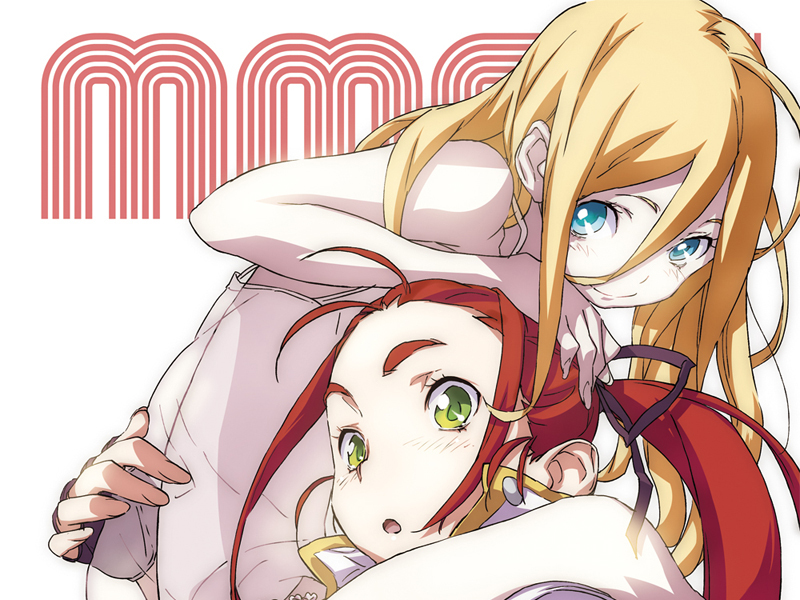物語の方法論は大分して、2つしかない。「普遍的な題材を普遍的に描く」か「個人的な題材を普遍的に描く」かのどちらかである。キルビル2について。日本版のみの副題、”the love story”。どんな作品でも恋愛ものとして宣伝すれば客は入るという配給会社の作品への冒涜的なやり口に、賢明な諸氏はもうずっと辟易し続けてきていると思うが、ことこの作品に関しては全く違和感 がない。KILL IS LOVE。KILL BILLは、LOVE BILLなのだ。愛は個別的であるがゆえに、つまりどの愛もどの愛と似ていないがゆえに、殺してまでそうしなければならぬ、最も極端にある「異常な愛」を描くことで、逆説的に「普遍的な愛」を描くことにこの作品は成功している。汗をかき、泥にまみれて、愛する者を殺し、トイレの床に転がり鼻水を流しながら”thank you”という主人公に、私は映画と人間性の正道を見る。あの”thank you”が心に少しもひっかかりを与えなかったなら、自分の感性が「汗くさくないこと」が主眼の”スタイリッシュ”な作品群に踏み荒らされておかしくなってきていることを真剣に疑った方がいい。早々に軌道修正しないと二度と戻ってこれなくなる。キルビル2は、個人的な題材(B級なるものへの愛)を普遍性にまで高めた傑作である。
キャシャーンについて。戦争と平和という普遍的なテーマを置こうとして、それが全く個人的動機に過ぎないことを全編に渡って露呈している。つまりこの映画のテーマとは、PV出身の監督が初めて映画を撮るに当たっての”作られた”テーマ性であり、初めての映画に気負うあまり、現代の世界が置かれている状況を取りいれよう安直に考え(それがカッコイイ態度だ、と思ったのかもしれない)、自身の素質を省みない全く皮相的に止まるテーマの繰り込みを行った結果である。人造人間誕生の設定が原作の「自身から進んで」から「父親に無理矢理」へ変更されてしまっているところから、この推測がある程度の的を射ていることが理解されよう。この変更点は同時に「キャシャーンがやらねば誰がやる」というあの決め台詞に込められた熱と意味性を完全に削ぎ落としてしまっており(街角にある”世界人類が平和でありますように”といった世迷い言ではなく、争いが本質的に不可避であることを自覚し、そこへの自分の態度を明確にしており、素晴らしい台詞だ)、「原作をよくわかっている」など という賞賛は全く当てはまるどころではないことが、表層的な装飾群に惑わされない少しでも真摯さを持つ視聴者なら、瞬時に理解できるだろう。おそらく無自覚的にではあろうが、監督は個人的な動機で原作をさえ、弄んだのである。作品の持つテーマとは、自身が世界と対面するときに何に固執しているかという点であり、ここが重要なのだが、”恣意的に選択できるものではない”。「戦争と平和」という巨大なテーマ(人類の持つ究極の命題の1つだ!)を扱うに、この監督の初期衝動は「初めての映画で頑張らなくっちゃ! イラク戦争で世界は大変だし、よぅし、戦争を批判しちゃえ!」程度の可愛らしくも絶望的に浅薄なものであり、あまりに脳天気すぎる。「飢えた子どもの前で文学は1枚のパンよりも有効なのか」という古い問いかけを持ち出すまでもなく、この映画は戦火に焼かれる子どもの前で明らかに有効ではない。そして、この映画は(真摯な)原作ファンの前でも明らかに有効ではない。それゆえに、この映画は完全に失敗している。更に言うなら、普段ほとんど邦画を見ない人間がこの映画の大量テレビCMとテーマソングにひかれて入館し、今後二度と邦画は見ないことを決心しながら出ていくというのは、充分にありそうな話だ。日本映画凋落の戦犯の1人とならないことを切に願う。キャシャーンは、普遍的題材を個人的欲望の充実に落とした駄作である。この世に物語が成立する条件は、つまるところ2種類しかない。「真実のように見える嘘」を描くか、「嘘のように見える真実」を描くか。キルビル2は後者であり、キャシャーンはどちらでもない、「真実のように見せたいまがい物」である。つまり、キャシャーンは物語の段階にすら達していない”フィルムに熱転写された何か”に過ぎない。
以前、ホームページの掲示板で書いた文章である。Googleのキャッシュから発見した。何故か今日再録しなければならないという気持ちになった。諸君が高天原の続きを求めているのは重々承知だが、今週は手を入れる時間が持てなかった。もうしばらく待たれたい。来週中には更新するつもりだが、これは更なる感想や萌え画像の到着を否定するものではない。ときに諸君は異性に自分の特殊性向を面罵されるのは好きだろうか。私は好きである。頭の中にある言葉のままに私を罵倒してくれる女性がいないものかと思う。一言で切り捨てるのではなく、それこそ延々と、わずかの反論も不可能なほどの執拗さと精密さで罵られたい。